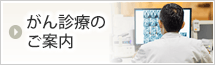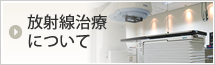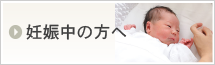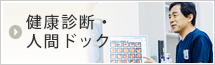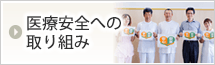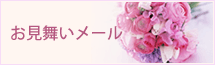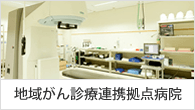臨床倫理について
社会保険田川病院 臨床倫理に関する方針
- ・患者の人権を尊重し、患者中心の医療を行います。
- ・患者の意思を十分確認し、自己決定権を尊重します。
- ・患者の個人情報を保護し、職務上の守秘義務を遵守します。
- ・倫理的な問題を含む医療行為に対しては、院内委員会にて倫理的、科学的観点から十分な審議を行い、最良の方針を決定します。
- ・生命倫理に関する法令を遵守し、ガイドラインを尊重した医療を行います。
当院では、この臨床倫理に関する方針を遵守した医療を提供するため、倫理問題について審議検討する医の倫理委員会があります。医の倫理委員会は、病院内の多職種と病院外からの一般の委員から成り立ちます。
臓器提供について
当院は、心停止下における臓器提供可能施設です。
「臓器提供意思表示カード(ドナーカード)」を持たれた患者さんやご家族から臓器提供の意思表示があった場合に、患者さんの意思を尊重し対応いたします。
宗教的理由による輸血拒否について
当院は、宗教的理由により輸血の治療を拒否する患者さんに対して、可能な限り輸血をしない治療を行います。ただし、輸血以外に生命の維持が困難な場合は、患者さんの同意がなくても輸血を行う相対的無輸血治療の方針とします。この方針に同意いただけない場合は、転院を勧めます。また、患者さん側から提示される輸血に関する「免責証明書」等の絶対的無輸血治療※に関する同意書に当院は署名しません。
※絶対的無輸血治療とは、輸血以外に救命手段がない状況でも輸血をしないことです。
治療拒否について
当院では、患者さんが治療拒否を示された場合、その時の意思判断能力に問題がないか確認の上、拒否した治療により生じる利益と不利益を提示し、その上で治療を拒否できる権利を認めます。ただし、感染症など本人の人権や自己決定権の尊重よりも公衆衛生や社会の利益を優先せざえるを得ない場合は、この権利が制限される場合があります。
虐待への対応について
当院の患者さんや利用者さんが児童虐待、高齢者虐待、障がい者虐待及びパートナーからの暴力(DV)等を受けた又は受けている場合の早期発見に努め、その疑いがあるときは、速やかに適切な公的機関に通報し、対応に協力します。
インフォームド・コンセント(説明と同意)について
当院では、患者さんが医師等から病状及び治療行為や検査などの必要性・安全生・危険性や治療方針、検査結果などの診療内容について十分説明を受け、理解・納得したうえで治療を受けられるよう支援します。患者さんが意思を表明できない場合や十分な判断能力が欠けると判断された場合(未成年を含む)は、ご家族等をインフォームド・コンセントの対象とします。
適切な意思決定支援について
すべての患者が、最善の医療・ケアを受けられるよう、多職種による医療・ケアチームで、患者や家族等に対し適切な説明と十分な話し合いをくり返し行い、患者本人の意思を尊重した医療・ケアを提供することを基本方針とし、以下においては厚労省等の各ガイドラインを規範とします。
1.人生の最終段階における医療・ケアの決定に関すること
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」
2.身寄りがない患者の医療における意思決定支援に関すること
「身寄りがない人の入院及び医療に係わる医師決定困難な人への支援に関するガイドライン」
3.認知症の患者の医療における意思決定支援に関すること
「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」
※当院におけるACP(アドバンス・ケア・プランニング)の取り組みについて
アドバンス・ケア・プランニングとは「人生会議」とも言われ、もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて、前もって考え、家族等や医療・ケアチームとくり返し話し合い、共有する取り組みの事です。
苦痛緩和目的の鎮静(セデーション)について
当院では、終末期の苦痛緩和を目的とし鎮静(セデーション)を行う場合、メリットとデメリットを慎重に考慮し倫理的な妥当性を検討した上で、適格に実施されることを目的に「がん患者の治療抵抗性の苦痛と鎮静に関する基本的な考え方の手引き」を原則とすることを基本方針とします。
当院で新たに実施する高難度を有する医療技術について
当院で新規に高難度医療技術を必要とする治療法については、保険適応で認められていても、当該部署で倫理面と医療安全面を十分に検討し、医の倫理委員会および関連委員会で審査します。導入後も定期的に評価し継続の可否を検討します。
治療上必要となった医薬品等の適応外使用について
医薬品及び医療機器は、医薬品医療機器法に基づき厚生労働省が承認した方法で使用することが求められています。しかし、当院での治療上、承認された方法以外での使用方法(適応外使用)が必要となった場合には、当院の臨床研究倫理委員会において使用の必要性があるか、有効性や安全性に問題ないか検証し、承認した上で使用します。また、適応外使用を行う場合は、医師等が文書で説明し、患者の同意を得ることとしていますが、十分な科学的根拠があり、複数の患者に有益であることが認められている場合には、文書等による説明・同意取得を例外的に簡略化し、当ホームページ上でその内容について情報公開(オプトアウト)をします。患者さんは、その内容を確認し、治療を拒否することができます。治療をくわしくお知りになりたい場合や治療を拒否したい場合は、問い合わせ先にご連絡ください。
身体行動制限について
当院では、患者の尊厳と権利を尊重し、身体行動制限による身体的・精神的弊害を理解し、身体行動制限廃止及び適性化に向けた意識のもと、緊急ややむを得ない場合を除き身体行動制限をしない医療の提供を行います。
その他の倫理的問題について
その他、臨床での倫理的問題については、多職種からなる検討会等で問題を共有し合い、解決に向けた話し合いを行います。解決に困難をきたす場合には、倫理コンサルテーションや医の倫理委員会で助言や方向性を諮ります。また、必要性や希望に応じて、患者や家族等を交え、なにが患者にとって最善となるかを話し合います。